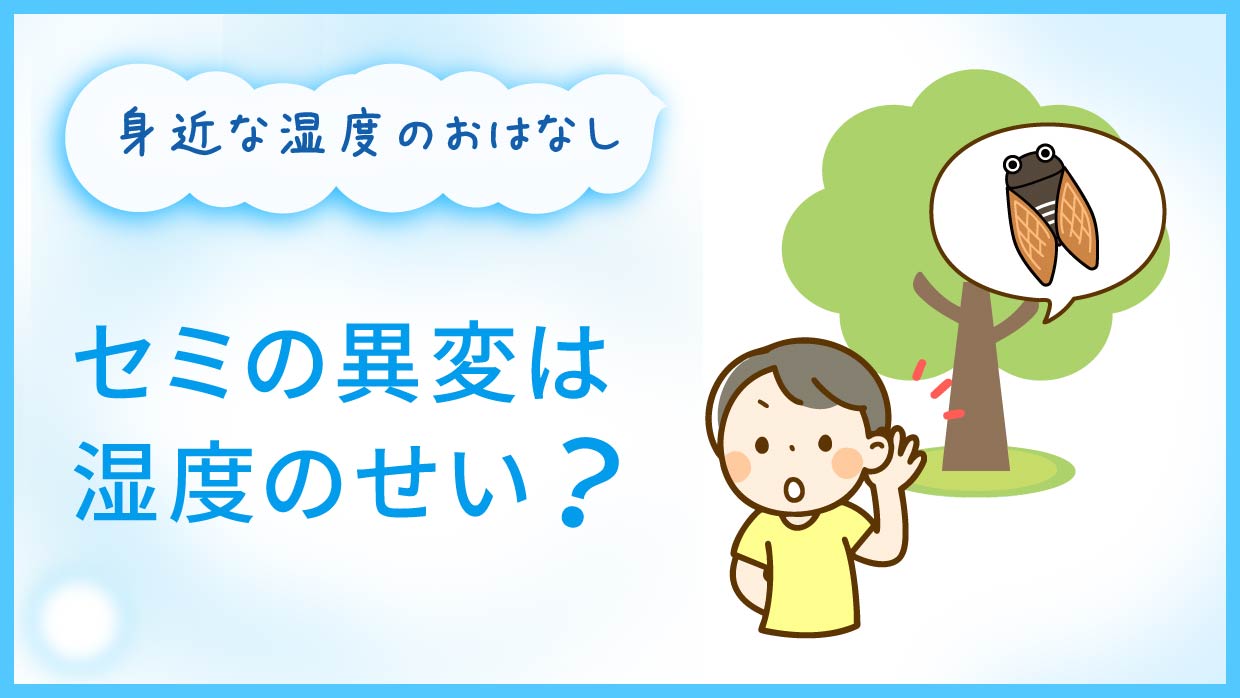
公開日:2025.07.25 身近な湿度のおはなし
セミの異変は湿度のせい?
ジメジメとした梅雨が明けると聞こえてくる、夏を知らせる「セミの鳴き声」。しかし、2025年の夏は、その声が少ないと感じる方が多くいらっしゃるかもしれません。それには、短かった梅雨やそれに続く急激な猛暑といった気象条件の変化が、セミの羽化のタイミングや成虫の活動に影響を与えたとの見解があります。
今回は、セミの羽化を左右する要素の一つ、湿度に注目して、夏の声が少なくなった理由をご紹介します。
セミの幼虫は、数年間もの地下生活を終えて、地上に這い上がり、木などにしがみついて羽化を行います。その際、柔らかい羽をゆっくりと伸ばしていくのですが、この時の湿度が羽の形成に大きな影響を与えます。羽をしっかり伸ばした状態で乾燥するのが理想ですが、湿度が高すぎると羽の乾燥が適切に進まず、十分に伸びきらないまま固まってしまいます。これでは、セミはうまく飛ぶことができず、天敵から逃れることも、パートナーを見つけることもできないまま、力尽きてしまう可能性が高くなります。
2025年は梅雨明けが早く、その後すぐに猛暑が訪れました。梅雨明け後の猛暑で地面の湿度が急激に変化したことが、セミの羽化に影響を与えた可能性が考えられます。
また猛暑は、無事に羽化したセミの成虫にとっても厳しい環境です。セミは体温調節が苦手なため、極端な暑さの中では活動を控える傾向があります。これはセミの活動時間や鳴く頻度にも影響を与えています。例えば、クマゼミは32℃程度、ミンミンゼミは35℃程度までしか鳴かないと言われているため、気温35℃以上の猛暑日には、セミがいても鳴いておらず、私たちが存在に気づいていない可能性があります。
そのため、たとえセミの数が例年通りであったとしても、日中の猛暑によって活動が抑制され、私たちの耳に届く鳴き声が少ないと感じるのです。
それでは、セミにとって理想の湿度条件はどのようなものでしょうか。セミの羽化は、一般的に夜から明け方にかけて行われます。この時間帯は、日中と比べて気温が下がり、湿度が適度に保たれやすいからです。
セミが地上に出てくるためには、地温が一定の温度になる必要があります。そして、羽化のプロセスでは、乾燥しすぎず、かといって湿度が過剰でもない、絶妙なバランスの湿度が求められます。乾燥しすぎると、体が固まりすぎて殻から出にくくなり、高すぎると羽が乾かず、うまく伸びません。気温や湿度があまりにも高い夏は、人間だけでなく、セミにとっても大変厳しい環境になっているようです。
セミだけでなく、夏の代表的な昆虫であるカブトムシやクワガタムシも、湿度の影響を大きく受けます。
カブトムシやクワガタムシの幼虫は、腐葉土や朽ち木の中で育ちます。これらの場所は、適度な水分を含んでいて、幼虫の成長に必要な湿度を保っています。もし環境が乾燥しすぎると、幼虫は弱ってしまい、うまく成長できません。逆に湿度が高すぎると、カビや雑菌が繁殖しやすくなり、病気になってしまうこともあります。
成虫になっても、彼らは乾燥に弱い生き物です。夜間に活動することが多いのも、日中の乾燥や高温を避けるためだと考えられています。飼育ケースでカブトムシやクワガタムシを飼う場合も、適度な湿度を保つことが大切とされており、湿度管理が飼育の成功に直結します。
私たちが普段目にしている昆虫たちは、実は非常に繊細な環境バランスの上に成り立っています。特に、セミの羽化やカブトムシ・クワガタムシの成長には、温度だけでなく湿度も、彼らの生死を左右する重要な要素となります。
夏、セミの鳴き声がいつもより控えめに聞こえたとしても、それは単に数が少ないだけでなく、特殊な気象条件が彼らのデリケートな生命活動に影響を与えているのかもしれません。猛暑を一緒に乗り越える仲間と思って、応援してあげましょう。

